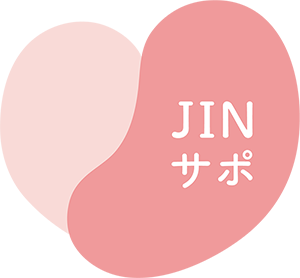心に残る患者さん ~ドクターズエッセイ~Vol.88(2016年8月号)
(先生の肩書は掲載当時のものです)

相川 厚 先生
東邦大学医学部腎臓学講座 教授
どの患者さんも同じように診なければいけない
私が2年間の外科研修を終え、慶應義塾大学病院泌尿器科に帰ったばかりのときの話です。部屋が隣通しの個室管理の2人の患者さんの主治医になりました。右側の部屋の患者さんは、まだ若く、母親から腎臓を提供された腎移植患者さんで、左側の部屋の患者さんは、お年寄りで、腎がんの全身転移になってしまった末期がんの患者さんでした。
腎移植患者のTさんは腎機能が低下してきた最中に重症の肺感染症になり、呼吸不全のため人工呼吸器が装着されていました。上級医のH先生は「彼はまだ若いので、何としても救命しなさい。」といわれ、必死になって、何日も病院に泊まり込み、1週間以上におよぶ重症管理をおこない、感染症を完治させ、呼吸器を取り外すことができました。残念ながら腎機能は廃絶し、透析に戻りました。この患者さんは群馬県の館林市の出身で、レスリングではインターハイや国体の候補選手で、長身でしっかりとした体型をしていました。ご家族からは透析に戻ったものの「助けていただき感謝します」とのお礼をいわれました。
しかしその部屋の隣の末期がんの患者さんは、死期が近づいたときに「隣の患者さんは、あんなに診てもらえて幸せだね」と私にそっと語りました。部屋の出入りの数が隣は多く、きっと会話も聞こえたかもしれません。「隣の患者さんと主治医は同じですよ」などとはいえませんでした。私はこの時、「隣の部屋なのになんでこの患者さんをもっと診てあげられなかったのか。同じ回数診察しなくとも、部屋に入り、声をかけてあげるだけでも違っていたかもしれない」と深く反省しました。最近は緩和ケアが充実して、末期がんの患者さんが穏やかに死を迎えることも増えてきています。しかし当時はそのようなものはなく、急性と慢性の患者さんが入り混じって同じ病棟で診療されていました。当時はその患者さんからいわれた言葉がショックで、決してこの気持ちを忘れてはいけないと、自分の心に刻み込みました。
それから10年たち、私が群馬県の太田総合病院の泌尿器科部長として出張したとき、館林市のある透析病院で透析をしているTさんにお会いしました。Tさんは相変わらずの人懐こい態度でご両親やお兄さんからもいっぱいの愛情を受けて透析をしていました。お母さんやお兄さんにもお会いし、また「あの時助けていただいてありがとうございました」とお礼の言葉をいただきました。その言葉を聞き、うれしくはありますが、隣の部屋の末期がんの患者さんのことを思い出し、「患者さんはどのような状態でも、同じように診なければいけない」ことがまた心の中でよみがえりました。
私は約2週間に1回の割合で、今も館林の透析病院にいっていますが、そこでは再会してから23年、はじめて出会ってから33年たったTさんが透析を続けています。