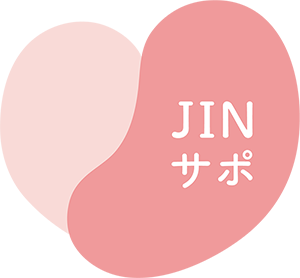体験談 / 一病息災 Vol.132(2025年4月号)
腎臓病と共にイキイキと暮らす方々に、腎臓サポート協会理事長 雁瀬美佐がインタビュー
(職業や治療法は、取材当時のものです *敬称略)
(職業や治療法は、取材当時のものです *敬称略)
- PD
宮野 清子 さん(みやの きよこ)

年齢も腎臓病も受け止めて、
腹膜透析で楽しく生きる
腎臓病になって40年、傘寿を超えた宮野清子さんの信条は、自分に起こるすべてを受け入れて前向きに生きること。幼少期に禅寺で学んだ「生」との向き合い方で、抗わず、人と比べず、努力することは惜しまず、工夫しながら楽しく過ごされています。
聞き手:雁瀬 美佐(腎臓サポート協会)
| 年齢(西暦) | 病歴・治療歴 |
|---|---|
| 1943年生まれ | |
| 43歳(1986年) | 極度の疲労感で病院を受診。IgA腎症と診断される |
| 71歳(2014年) | ひどい風邪を引き、頭痛と吐き気が続き受診。腹膜透析開始 |
| 79歳(2022年) | 両手骨折を機にヘルパー制度の利用開始 |
| 82歳(2025年) | 現在、腹膜透析(CAPD)1日4回、12年目 |
病気の自分を受け入れる
| 雁瀬 | 腎臓が悪いと診断されたのはいつ頃でしょうか。 |
| 宮野 | 43歳の時に母と10日ほど旅行に出かけました。金沢の美味しい食事と母と水入らずの時間を堪能して帰ってきましたが、翌朝起き上がることができませんでした。頭も上げられないほどの疲労感と、排尿時に少し痛みも感じたので近くの病院に行きました。血液検査の結果が悪かったようで大学病院での受診を勧められました。大学病院では、内科と婦人科、そして最後に腎臓内科で生検を受けてIgA腎症と診断されました。 |
| 雁瀬 | そこから保存期を過ごされていますね。塩分などの厳しい食事指導があったと思いますが。 |
| 宮野 | 我が家の食事はもともと煮物や和え物などの和食が中心でしたし、私は子どもの頃に禅寺で過ごした経験があったせいか、状況を受け入れることは自然にできたように思います。この命は天からいただいたもので、年齢も病気も私の身の内だと思っています。家族も野菜の食事に慣れていましたし、取り分けてから味の調整をするなど工夫すれば同じお料理をいただくことも可能ですのであまり不便は感じません。もともと楽観的な性格のせいか、工夫することが楽しいので工夫しながら今も変わらず普通に暮らしています。 |
| 雁瀬 | 透析導入となった時期について教えていただけますか。 |
| 宮野 | 保存期で30年近く頑張れていたので、当時の主治医の先生からは「宮野さんはもしかすると透析はしなくていいかもしれないよ」と言っていただいていましたが、いずれは透析をする時は来るだろうと覚悟はしていました。70歳を迎えてしばらくした時にひどい風邪を引いてしまいました。頭痛や吐き気などそれまでなかった症状が続き、何を食べても美味しく感じない日が多くなりました。それで「あぁ、その時が来たんだな」と自分でわかりました。そして「そろそろ透析を始める時期ですね」と自分から主治医の先生に聞いてみました。 |
| 雁瀬 | 普通は「そろそろ透析が必要です」と主治医から言われると、ひどく落ち込む患者さんが多いのですが。 |
| 宮野 | 私にとって透析は、私らしく生きていくための選択として自分で選んだので落ち込むなんていう考えは少しも頭にありませんでした。私は41歳の時に主人を亡くし、残された主人の事業を継ぎながら3人の子どもを育てました。その間には本当にいろいろな困難や問題がありましたけど、どの時も自分で考えて選択して歩んで来ました。前に進める方法があるのなら、選んで進む方が楽しいと思います。 |

選択できるなら腹膜透析(CAPD)
| 雁瀬 | 透析が必要になった時、自らCAPDを選択されていますね。 |
| 宮野 | 以前、フランスで腎臓病について学んだ知り合いの医師に私の病気のことを話した時、「もし将来、透析をすることになったらCAPDを選びなさい」と言われました。日本では血液透析が一般的だけど、ヨーロッパでは多くの患者がCAPDを選択し、週に何回も通院する血液透析よりも自宅で自由度の高い生活を送っていると聞いていました。ですので、選択できるのならばCAPDと決めていました。 |
| 雁瀬 | CAPDの生活はいかがですか。 |
| 宮野 | 生活に不安や不便を感じたことはありません。透析に掛かる時間はものの30分程度ですし、カテーテルを着けたり外したりもほんの一瞬のことです。毎日、朝は6時、お昼は12時、夕方は4時から6時の間、夜は9時から10時の間と大体の時間を決めておいて、そのつもりで予定を立てて自由に外出します。家族とも出かけますが、一人で車を運転して買い物にも行きます。お店の駐車場に停めた車の中で透析をすることもあれば、百貨店や美術館、劇場などの医務室を借りることもあります。駅にも、空港にも、新幹線の中にも医務室や多目的室はあるんです。事情を話せばどこでも親切に貸してくださいます。時々、外出先で透析のタイミングがずれることもありますが、食事と同じように考えて早くなったり遅くなったりすることもあると思えば気が楽です。私にとって透析はお腹のご飯です。 |

| 雁瀬 | 『お腹のご飯』って、とてもいい考え方ですね。CAPDを始めてから食事は変わりましたか。 |
| 宮野 | 腎臓病を患う前と後とそんなに大きくは変わりません。普段は、素材そのものの味を楽しむように心がけていますけど、もちろん外出先でのお食事は楽しみの一つです。たんぱく質の量を考えて少し残したり、後からかけるドレッシングやソースを控えたりもしますが、もし食べ過ぎてしまったとしてもその1日で帳尻をあわせようとしないで、一週間の中でトータルで考えています。それに最近は、年齢的に食べる量が自然と減ってきたので、ご飯は1日50~60gくらい、おかずや野菜の必要量をお皿に盛りつけます。いわゆるワンプレートの食事で、洗い物も少なく一石二鳥です。 |

自作のおせち
工夫して楽しい生活をこれからも
| 雁瀬 | 今でも旅行はよく行かれていますか。 |
| 宮野 | 旅行は年に2、3回は楽しんでいます。新幹線などの公共交通機関で移動する時には、CAPDに必要な荷物は薬も含めて事前に宿泊先に送ります。車で行く時はトランクに積みます。透析液は何かあった時のことも考えて1日分多めに持っていきます。それでもたまにはハプニングもあります。去年、青森まで大好きな縄文時代の遺跡を見に行きました。帰りに、電車の到着時間が遅れて駅で透析の時間になってしまいましたが、駅員さんに話すとすぐに場所を用意してくれました。ただ、新幹線の座席のコート掛けに透析バッグをかけて透析するつもりだったので携帯の点滴棒を東京への荷物に入れて送ってしまい、とても困りました。駅員さんが事務所のコートのハンガーラックを運んで来てくれて、それに透析バッグを吊るして無事に透析ができました。 |
| 雁瀬 | 透析バッグを吊るす棒?もお持ちなんですね。 |
| 宮野 | カメラ用の軽い三脚を息子に改造してもらいました。三脚なので折りたためば持ち運びができて重宝しています。透析バッグも、器械で温めたら取り出して、使い捨てカイロを貼って保温ラミネートに包んでおけば半日は温かいままで持ち運べます。もちろん、先生にちゃんと相談してからやっています。先生は「よくこういうことを考えるね」と言って褒めてくださるのでそれも励みです。楽に外出をするために、工夫して改善できると嬉しいものです。 |

| 雁瀬 | これからまだやりたいことはありますか。 |
| 宮野 | 旅行に行きたい場所がたくさんあります。それと、私はこの病気になってから茶道を習い始めたのですが、香道にも興味があります。 |
| 雁瀬 | お着物も素敵です。 |
| 宮野 | 母が残してくれた着物は外出着として活躍しています。CAPDのカテーテル設置手術の時、帯に当たらないように位置を少し下げてもらいました。着物でもCAPDには支障はありません。 |
| 雁瀬 | 同じ病気の患者さんにメッセージをお願いします。 |
| 宮野 | 毎日の食事の管理がとても重要だと思います。治る病気ではないので、現状を維持していくための努力が必要です。先生や管理栄養士さんの指導を守ることと、家族の理解と協力も大切だと思います。あとは、いろいろなことに興味を持って生活に工夫をしてそれを楽しむことと、現実を受け入れて前向きに行動することでしょうか。受け入れることは諦めることではありません。私は、腎臓病を受け入れたから今でも楽しく生活することができていると思っています。そして、こんなに生活を楽しめるのはCAPDを選んだからだと思っています。 |


縄文時代の遺跡(青森)への旅
インタビューを終えて
30年もの保存期を経て、CAPDを始めて12年目。この長い闘病を全く感じさせない落ち着き、お着物や茶道などの日本の文化を嗜む生活がある素敵な方でした。受け入れること、工夫すること、楽しむことが、腎臓病であっても無くても、生を彩る大切なことだと教えていただきました。
雁瀬美佐